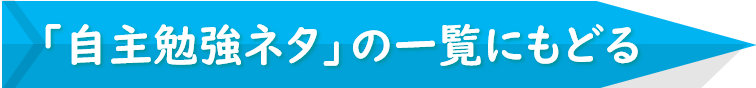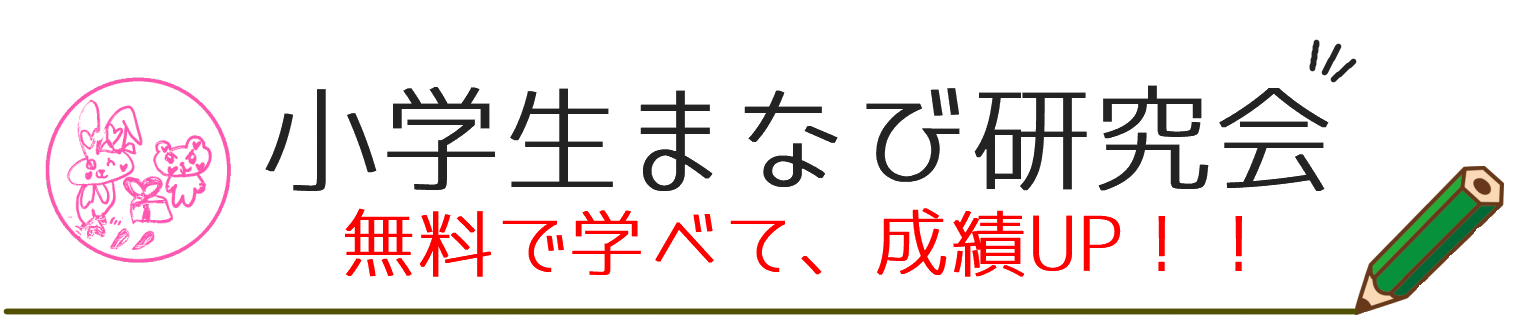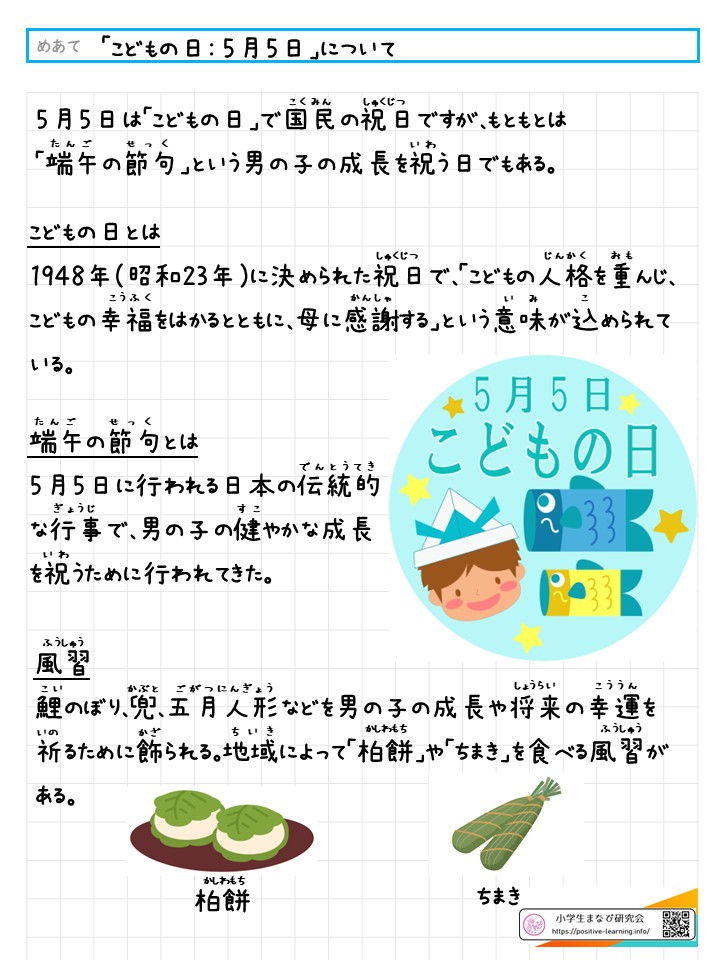【社会】「こどもの日」|小学3~6年生向け自主学習ノート
「こどもの日」について、小学生にも分かりやすくまとめています。自主学習や家庭学習で使える自学ノートの書き方例も紹介。通信教育やタブレット学習の補助教材としても活用できます。

ゆーちゃん
先生!!5月5日は「こどもの日」です。

先生
知ってますよ。どうかしましたか?

ゆーちゃん
こどもの日は、こどもが偉いんです。

先生
違います。こどもの幸せを願うとともに、親にも感謝をする日です。

ゆーちゃん
えっ!そうなの!?

先生
正しく理解しましょう!
自主学習ノートの書き方(例)
5月5日
5月5日は「こどもの日」で国民の祝日ですが、もともとは「端午の節句」という男の子の成長を祝う日でもあります。
こどもの日とは
1948年(昭和23年)に決められた祝日で、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」という意味が込められています。
端午の節句(たんごのせっく)とは
端午の節句は、5月5日に行われる日本の伝統的な行事で、男の子の健やかな成長を祝うために行われてきました。
この行事は奈良時代に中国から伝わり、もともとは病気や災いを防ぐための行事でした。
それが江戸時代になると武士の家に男の子が生まれるとお祝いをするようになり、この風習が広まり現在も続いています。
風習(ふうしゅう)
飾るもの
「鯉のぼり」
中国の昔話の『登竜門』が元になっているとされています。
この話は、急流を登り切った鯉が龍になったという話です。
「兜」・「五月人形」
成長や将来の幸運を祈るために飾られます。

鯉のぼり

兜・五月人形
料理
端午の節句には、地域によって「柏餅」や「ちまき」を食べる風習があります。
柏餅は、柏の葉で包んだ餅で、柏の葉は新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、子孫繁栄を象徴しています。
また、ちまきはもち米を葉で包んだもので、これは邪気を払い、健康を祈る意味があります。
こどもの日や端午の節句は、子どもの成長をお祝いする日です。
ですが、それだけではなく、毎日見守ってくれている家族やまわりの人たちへ、「ありがとう」の気持ちを伝える日にもしてみましょう!

柏餅

ちまき